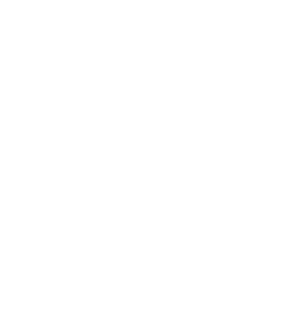はじめに
前回のコラムではAI時代における感情労働の増加と課題について説明しました。
今回はその課題に対処するために感情解析テクノロジーを用いる手法について説明します。
感情労働の現状と課題
手法の説明に入る前に、再度現状と課題についての要点を説明します。

(1) ITやAIの発展により、肉体労働と頭脳労働の多くは自動化・効率化されつつあるが、感情労働はそれが難しく、以下の理由により労働活動に占める比重が高まっている。
- 感情労働は機械で代替しにくい
- AIがルーチン業務を担うことで、人間労働の価値は「対人関係」や「創造性」に重点が置かれ、感情労働を伴う仕事がより重視されるようになる。
- 生活や仕事のデジタル化が進むにつれて、多くの人々がそれを使わざるを得なくなってストレスが増大し、「人間らしい対応」へのニーズが高まっている。
- 先進国では製造業の割合が減り、「感情労働」を求める分野のサービス業の比重が高まっている。
(2) 感情労働は以下のような点で労働者の負担が大きい。
- 自分の本当の気持ちとは異なる感情を表現しなければならないためストレスが溜まりやすくなる(感情不一致)
- 相手の感情に寄り添って共感し過ぎると自分自身の感情が疲弊してしまう(共感疲労)
- 長時間にわたる感情労働により心身ともに疲弊し意欲を失ってしまう(燃え尽き症候群)
今回のコラムでは、音声感情解析テクノロジーを用いて、感情労働の増加に伴う労働者の負担を取り除く手法を紹介しますのでご一読下さい。
表層演技と深層演技
感情労働という概念を提唱した米国の社会学者ホックシールド氏の著書では感情管理には2つの種類があると述べられています。
表層演技と深層演技です。
前者は俳優や女優の演技のようなもので顧客に対して自分が適切な感情を持っていると思ってもらう為に声や表情、振舞いを装うことを言い、飛行機に搭乗する際にCAが職業的な笑顔で迎えてくれる場合がこれに相当します。
これは職業として自分の本当の気持ちとは異なる感情を演技表現しているわけです。
この演技に全くストレスを感じない労働者もいますし、高いストレスを感じる労働者もます。
同じ労働者でも体調や精神状態によりストレスを感じる時もあれば無い時もあります。
ストレスを感じる場合の状況は「感情の不一致」に相当します。
後者は自らの感情そのものを制御して本当に嬉しい、ほんとうに悲しいと思って顧客に接することを言います。
成果を上げている営業マンは深層演技で感情をコントロールすることが上手く、顧客の喜びや悲しみに心の底から共感することが出来ると言われます。
しかし、この感情演技を続けていると、自分自身の感情が疲弊して「共感疲労」を起こす場合があり、なおかつその状態に自分自身では気が付かないことがしばしばあるように思われます。
人事管理に必要な感情管理
労働者が「感情不一致」によりストレスを感じ、「共感疲労」によりいつのまにか精神疲労が溜まり、場合によっては「燃え尽き症候群」の症状を呈してしまうことは、雇用主である企業や団体にとっても労働者本人にとっても好ましいことでは無く、この労働者の感情状態を本人にとっても雇用主側にとっても適切に保つことが大切です。
最近は企業の持続的な成長や生産性向上を目指す為には、従業員の心身の健康や幸福を重視した経営手法が大事であるとの認識が拡がり、単なる福利厚生の充実ではなく、従業員の働きがいや、仕事への愛着、熱意を高めることで、企業全体のパフォーマンスを向上させるという考え方が認識され始めてきました。
これはウエルビーイング経営と言われます。
この経営手法では従来の人事管理では重視されていなかった「感情管理」が非常に重要になります。
ウエルビーイング経営を実践する為には従業員への様々な支援が必要になります。
特に以下の5つが重要です。
- 身体的健康の向上
- 精神的健康の向上
- 働きがいの向上
- 社会的つながりの強化
- 経済的安定
この中で従来あまり対策が打たれていないものが精神的健康の向上に対する支援でしょう。
今まで元気で仲間からも尊敬され職場のリーダー的存在だった人が、ある日突然出勤しなくなり、うつ状態と診断されて長期休暇を余儀なくされるケース(燃え尽き症候群の症状:世界保健機関(WHO)が2019年に「職業性ストレスによる健康問題」として認定)や、突然の退職の申し出を筆者の回りでも何度か経験しました。
このような問題が発生する理由の大きな理由の一つは、その人が精神的に健康であるかどうかを簡単に知る手段があまりなく、本人の申告に頼るしかないからと思われます。

ここで「感情管理」が重要になります。
本人の申告に頼ることなく従業員の感情状態、特に深層演技に伴う感情の状態とその時系列変化を人事担当部門が客観的に知ることができれば燃え尽き症候群や突然退職の症状が出る前に、業務負担の適正化、ミスを責めない心理的安全性の確保、適切な休息の推奨、1on1ミーティングの実施、早期のメディカルカウンセリング、等いろいろな手を打てたことでしょう。
しかし、手遅れになる場合が多いのが現状です。
従業員の感情を可視化してストレスレベルが高い従業員を早期発見できるツールが是非とも必要です。
「ALICe」の活用法
ここでお勧めなのが音声感情解析テクノロジーです。
当社が提供している感情解析ソリューション「ALICe」は話者の様々な感情を数値化して出力可能なツールです。
以前のコラムで説明したように、感情には基本感情と高次元感情がありますが「ALICe」はこのどちらも数値化して出力可能です。
人事業務で必要となる感情は深層演技に対応する感情です。
これは高次元感情に相当し、「情熱」、「不安」、「ストレス」、「自信」、「集中」、「Anticipation(期待や演技度)」、等の高次元感情を数値化し、そこから話者のパーソナリティー、業務特性、就業意欲、責任感、問題解決、成長意欲、行動力、等のウエルビーイング情報を出力することができます。
従って、人事業務に必要な情報を提供することが可能になります。
手法は簡単で、被験者に数十秒から数分の短時間で簡単な質問をPC上に出し、その回答をPCに声に出して言ってもらうだけです。
この音声を「ALICe」にかけると感情情報とそれから計算されたウエルビーイング情報を得ることができます。

これらの情報を1年に1回程度スナップショット的に収集するのでは無く、毎月あるいは毎週収集するようにして時系列変化の測定データを収集します。
測定データが突然大きく変化した場合や時系列変化の振れが大きく不安定なデータになった場合には大きな感情負荷が被測定者にかかっている場合ですので、ヒアリングやコンサルなどの人事施策的な介入が必要と判断されます。
手遅れになる前に早期発見・早期対処ができるようになります。
身体の病気の予防は人間ドックで早期発見し必要に応じて直ぐに治療に入るように、精神的健康はまず感情チェックから始めることをお勧めいたします。

本ソリューションに興味をお持ちの方は当社までお問い合わせください。